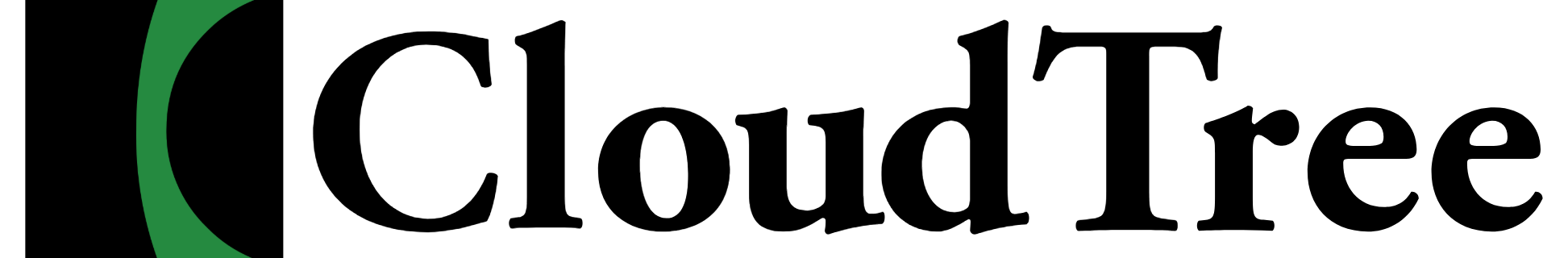月30時間以上の転記・集計作業をゼロに。
手書き日報のデジタル化が、全社DXの強固な礎を築いた舞台裏
導入前の課題: 毎日繰り返される手作業での集計作業。しかしすべては「終わってからでないとわからない」という悔しさ
小田エンジニアリング株式会社様では、長年にわたり、製造現場での日報を手書きで運用されていました。各従業員はその日に取り組んだ業務について、その案件名、工程数、工数を日報用紙に記入します。明朝に用紙は事務所に集められ、事務員が1~2時間かけて内容を確認し、さらに案件ごとに工数を集計して紙の棒グラフに積算させていくという、単調だが根気のいる作業が発生していました。
この方式は運用の柔軟性こそ高いものの、人件費コストが大きく、かつ他にも様々な問題を抱えていました。
「もっと早く知りたかった…」
集計された紙のグラフは社長様の手元にも回覧されますが、それはその案件に関する業務がすべて完了した後でした。製造工程で問題が発生し遅れが生じているとしても、ただでさえ外出も多い社長様が、的確にそれを把握するのは困難でした。
「これだけじゃあ何とも…」
グラフはあくまで工程ごとの工数積算であり、「どの工程でどれくらいの工数がかかったか」しか把握することはできませんでした。金型製造においては、各ワークが複雑な工程を経て製作されていきますが、その時間軸に沿った工数分布や、ワークごとの分布の違いといった、より詳細な分析は別途実施する必要があり、しかもそれは手書きの日報用紙から行わなければならず、二次利用は事実上不可能な状態でした。
「以前のあの案件の資料はどこだっけ?」
記入された日報用紙も、集計結果であるグラフも、すべては紙の資料であり、保管には相応の場所を必要とします。しかも、保管場所の詳細は担当の事務員しかわからず、営業活動などで過去の案件を参考にしようにも、そのためには毎回事務員に依頼する必要がありました。
日報周辺業務に費やされる時間は、毎月30時間を超え、人件費に換算すると年間100万円以上のコストとなっていました。そしてそれだけの支出をしても、手元に残るのはキャビネットを埋め尽くす紙の山だけ、という状況だったのです。
要件定義と選定: 「理想」と「現実」のバランス点
日報入力のデジタル化は、これらの課題を解決する明確な一手でした。集計を自動化し、入力された生データを多様な分析に活用できる利点は、誰の目にも明らかでした。
そのため、小田エンジニアリング様と弊社で協力して、状況と課題を整理し、まずは目指すべき未来の姿を明確にするところから始めました。
目指すべき未来の姿
こちらは、比較的スムーズにまとまりました。
- 入力された日報データを簡単に集計・分析できること。また、入力の翌朝にはそれができるようになっていること。(リアルタイム性向上)
- 入力データや集計結果を取り出し、エクセルなどを利用したデータ操作が可能であること。(分析の自由度向上)
- 集計・分析結果を、必要とする全従業員が、いつでもすぐに確認できること。(データ利用の自由度向上)
要件定義
続いて、上記の未来に到達するために、デジタルツールに求められる仕様を、もう少し具体的に言語化していきました。
| 要件 | 理由 |
|---|---|
| 1. パソコンで入力可能 | ほぼすべての工程に、インターネット通信ありのWindowsパソコンが配備されているため。 |
| 2. 従来の日報用紙のような画面設計 | デジタルツール移行の心理的抵抗を軽減するため。従業員さんの年代は様々であり、デジタルデバイスへの適応性についても、個人間のばらつきが大きいため、複雑な入力フローは避けたい。 |
| 3. 入力画面をずっと表示しておくことができる | 紙の日報用紙の利点として、作業中に机の横に常に置いておくことができた。これにより、一つの作業が完了した際に、その内容を素早く記入できた。デジタルツールでもそういった使い方がしたい。 |
| 4. OSやアプリケーションのアップデートなどによる更新の手間が生じにくい | 複雑な依存関係をもつ環境で構築されたデジタルツールは、依存先環境の変化により、たびたびアップデートする必要が生じる可能性があり、運用の手間が大きくなる。具体的にはwebアプリ形式が望ましい。 |
| 5. CSVでのデータ出力が可能 | 入力された日報データや集計結果を気軽にCSV出力できることで、定形の分析以外にも、状況に応じた柔軟な集計・分析を実施することができるようになる。 |
| 6. 外部から保守可能 | 小田エンジニアリング様には常駐のシステム要員がいないため、初歩的な運用作業以外は、外部(弊社)から実施できるようにしておきたい。 |
導入に必須の要件に混ざって、導入時に従業員様に生じる負荷や抵抗感をできるだけ抑えるための配慮も複数含まれています(2や3)。一見、非合理的で無駄であるようにも見えますが、しかし素晴らしいツールも定着しなければ意味がありません。実際、後々いくつか問題が浮上しながらも、比較的スムーズに導入が進んだのは、こういった配慮を盛り込むことへのご理解を示していただけたことが大きかったと考えています。
選定
要件定義の結果を受けて、条件を満たす解決策の選定を進めましたが、その選択は簡単ではありませんでした。市販の生産管理ツールも検討したものの、機能が多すぎて高価だったり、逆に安価なツールだと、柔軟な画面設計や、基本的なデータのCSV出力ができなかったりと、「帯に短したすきに長し」の状態でした。
そこで弊社は、長期的なランニングコストを抑えつつ、小田エンジニアリング様の業務に完璧にフィットする柔軟性を実現するため、Google Apps Scriptとスプレッドシートをベースにした、オーダーメイドの日報入力ツールの開発をご提案しました。
これは、既製品ではなくプログラミングによる開発となるため、その設計や運用に極めて高い自由度、柔軟性、拡張性を確保できます。しかし一方で、完全クラウド環境での構築となるため、開発体制を構築する負荷が軽く、イニシャルコストや開発期間を比較的抑えることが可能です。
結果、オーダーメイド開発にて進めていくこととなりました。
定着への道のり: 「システム」と「人間」の最適な接点を探して
開発〜導入準備〜導入と進んでいく中で、事前の想定には含まれていなかった問題がいくつか発生しました。なかでも、最も重要であったのは「案件IDの設計方式」の見直しと、それに伴う「全社的なID管理の定着」でした。
従来、「去年の〇〇会社さんのカバーのやつ」といった曖昧な表現で成り立っていた社内コミュニケーションを、システムが理解できる一意のIDに置き換える必要がありました。当初、システム効率を優先し、無機質な文字列のIDを提案させていただいていたところ、導入に向けたトレーニングを進める中で、「覚えにくいし、口頭で伝えられない」という意見が上がりました。
「IDを見ただけで、ああ、あの客先のあの製品のことだな、って分かるようなものじゃないと、結局毎回パソコンの前に行かなきゃならない。それじゃ定着しない。」
この意見を受けて、現場の皆様とも議論を重ねつつ、重複を避けつつも、人間が認識しやすい規則性を持った次のようなID体系を、共同で設計しました。
①AA ②1234 - ③250924 ④B
(① 取引先コード 2文字 ② 製品コード 4文字 - ③ 案件発生日 ④ 案件カテゴリ)
このIDは、日常業務で口にしても比較的スムーズに伝達できます。かつ、案件IDを見ただけで、その内容をある程度推測できるようになりました。案件発生時には、まず営業部門で案件IDが採番され、システムに登録されます。現場では、帳票や図面に記入されたその案件IDを入力するだけで、簡単に日報を入力したり、関連情報が自動で表示されるようになりました。
新しい業務フローが定着するまでには粘り強いトレーニングが必要ですが、理想と現実の素晴らしいバランス感覚で設計された今回の案件IDは、運用の定着と、従業員の皆様への「IDでもって情報を管理している」という意識の浸透に、大きく貢献したと思います。
導入後の成果: 月間30時間の削減と、それ以上に大きな「意識の変革」
ツールの導入による直接的な効果は、劇的でした。
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| 日報の集計業務 | 毎日1〜2時間(月間30時間以上) | ゼロ(ボタン一つでただちに自動集計)。集計のミスもゼロ。 |
| 案件ごとの工数把握のタイミング | 案件終了後に紙で確認 | リアルタイムでいつでも確認可能 |
| データ活用 | 棒グラフでの工程ごとの工数積算のみ(元データが紙であり、二次活用不可) | CSVで出力し、自由に多角的な分析が可能。新たな集計・分析機能を追加することも可能。 |
| 日報入力の手間 | 紙に手書きなので自由度は高い。しかし毎日繰り返し同じことを記入する必要があり、記入ミスや勘違いも生じる。 | IDを利用した入力補助機能が多く、繰り返し入力の手間が減り、入力ミスも減った。 |
| 保管場所 | 日報も分析結果もすべて紙であるため、大きく場所を占有する。正確な保管場所は担当者しかわからない。 | すべてのデータは最初からデジタルであり、保管場所は必要なし。また過去のデータも一覧画面から即座に表示可能で、探す手間もなくなった。 |
今回の取り組みにより、日報の集計業務はほぼ完全に自動化され、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。同時に、管理部門はリアルタイムで案件の進捗や採算状況を把握し、迅速な対応を行えるようになりました。
しかし、このプロジェクトがもたらした最大の成果は、単なる時間削減ではありません。1つは、「業務情報のすべてをIDで管理する」という文化が、会社全体に根付いたこと。そしてもう1つは、日報ツールの開発に伴い、案件・顧客・従業員といった、会社を運営していく上での基盤となるデータが、実際のデータベースとして機能し始めたことです。
工数だけでなく、図面、仕様書、顧客とのやり取り、仕入れ、出荷など、業務に関わるあらゆる情報がIDという共通言語で結びつけられ、データベースで管理されている。この「認識的な基盤」と「電子的な基盤」が構築されたことこそが、小田エンジニアリング様が今後さらにDXを加速させていく上での、最も強固な礎となったのです。
お客様の声

「正直、最初は『うちの業務にあったツールが存在するのか』『従業員が使ってくれるのか』『思い描いたような成果を達成できるのか』など、不安は尽きませんでした。しかし、実際に出てきた画面を見た時、いつもの紙の日報用紙によく似ており、少し安心しました。入力も、IDを入れると関連情報がパッと出るので、むしろ以前より楽になりました。
何より変わったのは、事務所や現場との連携です。今までは曖昧な表現で指示を出すことで伝達ミスが生じたり、過去の情報を見るために事務員にお願いをする必要がありましたが、それらが一切なくなりました。営業的な回答でも、社内状況をちゃんと把握できていますので、即座に回答することができます。リアルタイムで数字が見える安心感は、想像以上でした。
一部の従業員の間だけでなく、会社全体で情報を正確に扱うという文化が生まれたことが、一番の財産だと思います。」
小田エンジニアリング株式会社
代表取締役 渡辺 計人 様