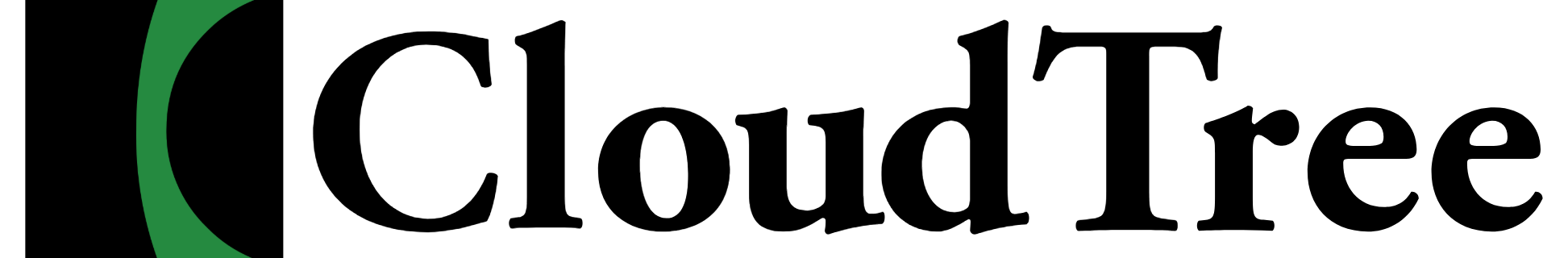年間500時間の帳票業務を50%削減。
Excelとフォルダの混沌から脱却し、全社の情報共有を加速させた「データ連携基盤」構築の裏側
導入前の課題: 毎日数時間が消えていく、終わりなき「探し、写し、保存する」作業
小田エンジニアリング様の営業・管理部門では、日々発生する多種多様な帳票の作成と管理が、業務を圧迫する大きな要因となっていました。見積書、請求書、注文書といった定型的な書類から、製造現場への指示書、品質検査書に至るまで、そのすべてがExcelで作成されていました。
「この案件の帳票作成に使えそうな類似案件って、どれかなぁ…」
帳票作成のたびに、過去の類似ファイルを探し出し、コピーして内容を書き換える。このプロセスには、常に「探し出す時間」と「定型の項目を記入する時間」、さらには「変更・削除漏れによる入力ミス」のリスクがつきまといました。
また、作成後のファイル保管も各人の裁量に委ねられていたため、管理面でも多くの課題を抱えていました。
「あの案件の見積書、最終版はどれだっけ?」
一つの案件で、見積書を複数回提出するのは日常茶飯事です。そのため似たような帳票も多く、後から経過を判断するのは、担当者でさえ難しい場合も。また保管忘れや保管場所の間違いも頻発し、必要な時に必要な書類が見つからない、という事態も少なくありませんでした。
「この指示書、フォーマットが少し違うな…」
顧客や案件によっても必要な情報が異なるため、レイアウトに若干の修正を加えることは頻繁にあります。しかしフォーマットの管理も各担当者任せとなっているため、修正後のフォーマットを使いまわしてしまうことで、同じような案件でも、担当者間でレイアウトの差が拡大していきます。結果、書面上から必要な情報を探し出すのに時間がかかります。
一つ一つは小さな手間でも、日に数十回と繰り返されることで、その負荷は雪だるま式に膨れ上がります。わずか4〜5名の部門にもかかわらず、全員で合わせると1日に数時間が、こうした付加価値を生まない帳票関連業務に消えていました。
要件定義と選定: 「ペーパーレス」の幻想を捨て、「現場の現実」から導き出した最適解
帳票作成の際の定型部分の入力を自動化し、また同時に、その発行と保管を管理することで、こうした帳票管理業務につきまとう時間のロスを、大幅に低減できる可能性がありました。しかも、以前に導入させていただいていたデジタル日報ツールが既に稼働していたため、新たな情報入力の手間をほとんど発生させることなく、必要な情報の多くを流用することが可能でした。
我々は早速、達成されるべき未来の姿をはっきりさせるべく、検討を開始しました。
ペーパーレス化の検討と断念
プロジェクトの冒頭、「せっかくだから、現場も含めた完全なペーパーレス化を目指す」という目標を提案していました。しかしながら、私たちは現場の業務フローを詳細にヒアリングし、共にシミュレーションを重ねる中で、あえて「今回はペーパーレス化を見送る」という結論に達しました。
なぜなら製造現場では、図面中の指示やメモなど、手書きでなければかえって手間がかかったり、業務の機動力が低下する実態が数多くありました。さらに、各ワークに添付される現品票など、直接情報を記載できない物体に情報を付随させる手段としても、やはり紙の優位性は揺るぎないものでした。
例えタブレットのようなデバイスを導入しても、その恩恵は限定的であり、完全にペーパーレス化できる帳票は限られていました。そうなると、紙とデバイスという二つの媒体による運用となってしまう可能性が高く、例え紙を減らせたとしても、かえって業務効率が低下する可能性がありました。高齢の職人さんも多い中で、効果も曖昧なままに、無理にやり方を変えることは、混乱を招き、DXへの不信感を植え付けかねないと判断したのです。
要件定義と選定
結果私たちは、最もメリットが大きく、かつデメリットの少ない「帳票の入力と管理の自動化・効率化」にスコープを絞り込みました。これにより、直接関係するのは営業と管理部門のみとなり、要件定義もかなりシンプルになりました。
| 要件 | 理由 |
|---|---|
| 1. エクセルまたはスプレッドシートで作成したフォーマット(ひな型)を利用できること | フォーマットは適宜更新したいので、非エンジニアの管理者でも手軽に編集できるようにしたい。 |
| 2. 作成ボタンを押すと、フォーマットを複製して新しい帳票ファイルを作成し、所定の保管フォルダに保存すること。 | あらかじめ設定した保管場所にファイルを自動で割り振ることで、ミスや忘れによりファイルが行方不明になることを防ぐ。 |
| 3. さらに、定型の入力項目を自動入力した上で、ユーザーが編集可能な状態で表示すること。 | 帳票ごとの詳細な内容(例: 見積書の記載品目や仕様詳細など)は、ユーザーが直接ファイルに入力する方が早い。そのため、作成した帳票ファイルを編集可能な状態でユーザーに提示する。 |
| 4. 発行ボタンを押すと、帳票ファイルを自動でPDFに変換し、所定の保管フォルダに保存すること。 | 3でのユーザーによる編集・確認後に、その状態でPDF変換することができる。PDFも行方不明にならないように自動で保管。 |
| 5. 一覧画面には、帳票の基本的な情報に加えて、作成された帳票ファイルやPDFファイルへのリンクが表示させ、いつでも開けられるようにすること。 | 2や4で作成されたファイル類は、すべて即座にリンクが取得され、一覧画面に表示される。これにより、所定のフォルダを手動で開かなくても、リンクから対象ファイルを直接開くことができる。 |
| 6. OSやアプリケーションのアップデートなどによる更新の手間が生じにくい | 複雑な依存関係をもつ環境で構築されたデジタルツールは、依存先環境の変化により、たびたびアップデートする必要が生じる可能性があり、運用の手間が大きくなる。具体的にはwebアプリ形式が望ましい。 |
| 7. 外部から保守可能 | 小田エンジニアリング様には常駐のシステム要員がいないため、初歩的な運用作業以外は、外部(弊社)から実施できるようにしておきたい。 |
| 8. デジタル日報で利用しているデータベースを共用できること。 | 既存のデータベースの情報を流用することで、新たな情報入力の手間をなくせるから。 |
| 9. 各帳票は案件IDを紐付けて管理 | ある案件に関連する帳票の全体を素早く把握するため。 |
選定については、帳票に関するツールであるため、使い慣れた表計算アプリケーションベースであることが望ましい内容でした。そのため、デジタル日報で既に導入済みであることもあり、Google Apps Scriptとスプレッドシートをベースにしたオーダーメイド開発となりました。
定着への道のり: 「自動化」と「人間による介入」の最適なバランス点を探して
今回の実装において最もこだわったのは、金型というオーダーメイド品を専門に扱う小田エンジニアリング様の業務遂行に必要不可欠な、「柔軟性」の徹底した追及です。
1. 自動入力後の「手動修正」を許容
案件情報から定型項目を自動入力した後、あえてスプレッドシートのままユーザーに表示。イレギュラーな案件にも、担当者が自由に内容を追記・修正したり、配置を変更できるようにしました。
2. 現場主導の「レイアウト変更」
帳票のひな形は全てスプレッドシートで管理。これにより、「顧客名」や「案件名」といった自動入力の定型項目の配置は、弊社に依頼することなく、現場の管理者がいつでも簡単に変更できるように設計しました。
3. 「例外」を許す管理体制
突発的に発生する、どうしても自動入力には対応できないような特殊レイアウトの帳票も、管理対象に含められるようにしました。完全手動でファイルを作成して所定のフォルダに保管、その情報をシステムに登録すれば、他と同じように一覧画面で一元管理できるようにしました。自動入力は利用できませんが、作成後は他帳票と同様に管理できることで、「いざとなれば何とでもなる」という安心感につながり、ひいては新しいシステムへの信頼を生むと考えたからです。
4. 様々な帳票へ簡単に拡張可能
現場には無数の帳票がありますが、すべてを一気にシステムに取り込むと、業務が混乱する可能性があります。そのため、当初は 見積書、請求書、注文書などの基本的な帳票のみを対象としました。そして慣れてきた段階で、比較的簡単な修正で対象を他の帳票に自由に拡張できる設計としました。
自動化あるあるですが、あまりにも全自動化してしまうと、人間が介入する余地がなくなってしまい、柔軟な対応ができなくなります。これは、少量多品種やオーダーメイド対応が必要な場合は望ましくありません。そのため、要所要所で適切に人間が介入できる必要があるのですが、この柔軟性も行き過ぎてしまうと、管理が煩雑になったり、意図せずデータの破壊につながる可能性もあります。そのため、業務やユーザーの状況に合わせたバランス点を見出す必要があります。
少し脱線しましたが、今回はこういった徹底した柔軟性の確保により、比較的スムーズに導入と定着を進めることができました。実際、導入後数か月で、他の帳票に運用対象を拡張することができました。
導入後の成果: 50%超の時間削減と、部門を超えた「意識の共有」
ツールの導入は、営業・事務部門の働き方を劇的に変えました。
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| 帳票作成・管理時間 | 1日あたり合計2〜3時間 | 1日あたり1〜2時間(50%以上削減) |
| 過去の類似案件を探す時間 | 保管場所フォルダを開いて探す。見つからない場合は担当者に聞く。 | 一覧を確認し、ワンクリックでファイルを開いて詳細を確認。 |
| 入力ミス、管理ミス | 入力ミス、以前の入力の削除忘れ、保管忘れが頻繁に発生 | ゼロ |
| フォーマット管理 | 各自で管理。担当者が違えばフォーマットも異なる。 | 統一。変更する必要がある場合は、管理者がレイアウト変更可能。 |
| 全社的な情報共有を促進 | 担当者でないと経過や保管場所がわからない。 | 誰でも一覧を見ればわかる。 |
帳票作成は、「案件を選び、帳票の種類を選び、作成ボタンを押す」。定型項目が自動入力されて表示されるので、詳細を追加して、あとは「発行ボタンを押す」だけ。ファイルは自動で保管・管理され、案件IDに紐づき、一覧にはリンクが記載されます。もう誰も、ファイル探しに時間を浪費することはありません。
また、このツールは予想外の効果ももたらしました。案件IDと結びつけることで、全社的に利用されている案件情報一覧にも、発行された帳票へのリンクを設置することが可能になり、営業・事務部門に限らず、製造部門でも関連する社外向けの帳票を確認できるようになりました。結果、製造担当の社員が自工程に関係する顧客とのやり取りを自発的に確認し、その主旨に対応していく、という光景が見られるようになりました。
今回、スコープを絞り、ペーパーレス化に踏み込まなかった判断は、結果として大成功でした。もし影響範囲の広い現場の改革まで同時に進めていれば、負荷が増大し、プロジェクト全体が頓挫していたかもしれません。地に足のついた一歩が、結果的に最も大きな前進を生んだのです。
お客様の声

「以前は、Excelファイルが社内LANのあちこちに散乱し、どれが最新版なのか、どこにあるのか、担当者しか分からないという混沌とした状態でした。CloudTreeさんの提案は、単にツールを作るだけでなく、『なぜそうするのか』という根本的な部分から、我々と同じ目線で議論してくれたのが印象的でした。
導入したツールは驚くほどシンプルで、それでいて柔軟。今では、うちの事務スタッフが自分たちで帳票のレイアウトを修正しています。
単なる業務効率化ツールではなく、会社全体の情報を繋ぎ、社員の意識を変える『基盤』を創ってくれたのだと感謝しています。」
小田エンジニアリング株式会社
代表取締役 渡辺 計人 様